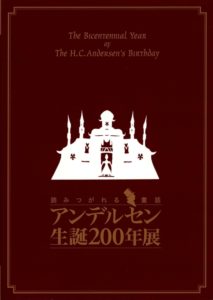今井良朗
挿絵と印刷の深いかかわり
ヴィルヘルム・ペダーセンの挿絵の入った『アンデルセン童話全集』が、デンマークで出版されたのは1849年のことである。当時挿絵に対する関心は高く、書物に挿絵が挿入されることはすでにめずらしいことではなかった。ただ、初期の挿絵は素朴な木版刷が主流で、書物の扉や巻頭を飾ったものがほとんどだった。
19世紀も半ばを過ぎると、アンデルセン童話にも挿絵は欠かせないものになっていくが、20世紀までの数10年間は、印刷技術の発展と合わせて、挿絵の表現性が飛躍的に向上していく時期である。カットとして挿入された挿絵は、絵が緻密になるにしたがって丹念に背景が描かれるようになり、1頁全体を占めるようになっていった。書物に対する関心は、挿絵の存在感が増すにしたがって一層高まっていった。アンデルセン童話の挿絵の歴史と絵本への展開は、そのままイラストレーションの発展と絵本の歴史でもある。
ペダーセンが描いたのは、鉛筆による素描の下絵で、出版されるときは木版画として複製される。ペダーセン画といっても彫版は専門の職人が行ったわけで、厳密にいえば原画である素描と木版画は異なった表現性を持っている。原画は今日のように写真製版によって忠実に複製印刷されていたわけではない。
挿絵は、当初濃淡のない線画と面だけの木版だったが、徐々に陰影や細部の表現が追求され、銅版彫刻や木口木版、石版などの新しい技術が生まれた。その結果表現がより具象的で緻密なものになっていった。それは、これらの印刷技術がそのまま表現の特性を表すことでもあった。イラストレーションの表現の確立には、書物と同様印刷技術が深く関わっていたのである。
19世紀後半は、印刷技術の上で様々な技術革新がなされ、複製技術が新しい段階を迎えた。書物の出版と合わせて、週刊誌『Punch』(1841年創刊)など、定期刊行物が驚くほど普及した時代でもある。いずれもイラストレーションが多用されたのが特徴で、興味深いのは、図版が写真を使用して製版されていたことである。19世紀はじめに発明された写真術は、すでに写真製版法としても応用されていた。当時の木口木版で用いられた製版法は、手工的ないわゆる写真版画である。この方法は、湿板写真の膜面をはがして木口に転写するか、木口に感光剤を塗布して直接画像を焼き付け、版下をつくり彫刻する方法である。水彩画やペン画の原画を版木に転写する方法がすでに採用されていた。木口木版は、絵画の複製技術としても、量産可能な最新の印刷技術としても重要な役割を担っていたのである。
もう一方の新しい印刷技術である石版は、紙に絵を描くのと同じように、石にクレヨンやとき墨で直接画像を描くことが可能で、比較的自由に表現することができた。こうした絵画的画像の再現性にすぐれていたことが、油彩、水彩、素描など、もとの表現方法にあわせた複製を可能にし、有効な印刷技術として受け入れられた。これは、今日一般的なオフセット印刷と同様の原理に基づく技術である。19世紀末、出版の隆盛を支えたのは、このような合理的なシステムを持った印刷工房が基盤にあったからである。
挿絵からイラストレーションへ
印刷技術の発達が、挿絵の価値を高めたことは間違いないが、精巧で緻密な表現に対する欲求が、新しい印刷技術の開発につながっていったことも事実である。
一つの物語に一つの挿絵という形態は、徐々に3画面、6画面とひろがっていく。書物は、挿絵で話題になることもめずらしくなく、挿絵画家は、物語からイメージを紡ぎ出すために想像力をかき立てられた。
フェアリーテールの世界も挿絵画家たちの想像力を刺激した。フェアリーテールは、口承されてきたおとぎ話の一つで、現実に存在しないもの、現実にあり得ないことなどを題材にする物語。妖精や魔物、お姫さまなどが登場するが、もともとは教訓的なものや教育的な意味を含んでいた。フェアリーテールは、ことばの世界から生まれたものだが、視覚的に見えるものとして描かれたときから書物の中で重要な役割を担うようになった。王子がカエルになる、おやゆびのように小さな少女、人間のように振る舞う動物、ことばから導かれるイメージは、視覚的な形を持つことで、より身近に人々の心の中に入っていった。そして、描く画家の違いによって、イメージが多様であることも明らかになっていった。書物のイラストレーションというジャンルが花開いたのである。
一つの場面を説明的に描いていた挿絵は、人物を描く場合でも、画家によって姿や形を描写するだけでなく、性格が与えられ、象徴的に描かれるようになっていった。挿絵は、著名な挿絵画家たちによって一段と魅力を増した。挿絵の入った豪華な書物は、クリスマスなどの贈り物として用いられ、ギフトブックと呼ばれたが、特に人気の高かったアーサー・ラッカムやエドモンド・デュラック、カイ・ニールセンらは、いずれもアンデルセン童話の挿絵を手がけ、秀逸なイラストレーションを数多く残した。華やかな挿絵で飾られた大型の豪華本は、誰もが手に入れられるわけではなく、純粋に子どもの本とはいえないが、印刷技術の制約を受けない新しいイラストレーションの様式をつくり出したことに、大きな意味があった。
これらの挿絵は、ようやく実用段階に入った凸版のカラー写真製版法=原色版が使われ、挿絵の世界ではじめて、原画がカラー印刷で忠実に再現された。写真製版による原画の再現は、水彩絵の具の柔らかなぼかしやペンによる自在な描線がそのまま表され、表情豊かな妖精たちが生き生きと表現された。デンマーク生まれのニールセンは、浮世絵の影響を強く受け、様式化された大胆な構成によって、際立った個性を発揮した。
挿絵の入った書物の成熟した形態は、物語の脇役だった挿絵がその主張を強めていった。このような傾向は、装飾性と商業性を強めたイラストレーションが独り歩きする危険性をはらんでいたが、イラストレーションの質を飛躍的に高めたこと、その後の絵本への影響も含めてイラストレーションの領域が確立したことは大きい。
挿絵本と絵本
「姫はみなで六人で、どれもきれいなかたばかりでしたが、わけても末の姫は、一番きれいでした。膚は、バラの花びらのように、すきとおるほどきめがこまかく、目は深い深い海のような青い色をしていました。けれども、おねえさんたちと同じく、足というものがなくて、胴の下は魚の尻尾になっているのでした。」これは、『人魚姫』を表す一節だが、これほど事細かく描写されていても、具体的な視覚像を誰もが共通に頭に描くわけではない。しかし、読者はここから想像力を刺激され、イメージをふくらませることができる。
ことばは、概念を共有できる優れた記号であるがきわめて曖昧なものでもある。イメージは一つの視覚像を結ぶわけではない。また単純に外界を写し取ったものではないし、現実の姿と完全に対応しているわけではない。イメージとはそのようなものである。
イメージとして頭の中に描かれる像は、ひろがりを持っている。個々人の頭の中で整理されたり、増幅したりしてある形として想起される。ことばは、単語一つだけ取り上げれば漠然としていても、前後や物語の全体の構成の中で、ことばが重なり合いイメージの輪郭を想起させる。
それに対してイラストレーションは、人魚姫の容姿のすべてを表し提示する。そのために、絵が想像力を阻害しイメージを限定してしまうという見方も出てくるが、そもそも、ことばとイラストレーションは、果たす機能、役割がまったく異なるものである。ことばによる人魚姫の描写は、アンデルセンの創造行為である。同様にアンデルセン童話から画家がイメージを描き出す行為も創造行為であり、画家の世界観、ものの見方がおのずと反映する。
アンデルセン童話は、ことばによって意味やイメージが十分表現されていて、物語として完成している。それだけに挿絵をつけることがそれほど簡単でないことは、これまでも多くのイラストレータが語ってきた。
初期の挿絵は、ことば主体の物語がまずあり、特徴的な一場面を抜き出しイメージを外面化したものがほとんどで、読者のイメージを補うものとしてあった。
ラッカムやデュラック、ニールセンの挿絵を見ると、アンデルセンの物語を忠実に視覚化することを前提にしながらも、イラストレータとして、いかに独自の解釈や見方を出せるか、腐心してきたかがよくわかる。それでも、ニールセンがどれほど個性的で独自の表現様式をつくり出しても、当時の文学と挿絵の関係は、それぞれの役割の違いを明確に意識していたといえるだろう。演劇の影響を受けたニールセンの挿絵は舞台の一場面を観る感覚に近く、その表現からさまざまな意味やイメージを読み取ることができるが、あくまでも独立した一枚の絵として完結しているのである。
一方、1870年ころには、物語をダイジェスト化したものが見られるようになり、挿絵の数が徐々に増えていった。ダイジェスト化の背景には、子どものために分かりやすくするなどの理由が考えられるが、結果的に童話は、二つの流れを生み出した。一つは文学として、あくまでも挿絵は文学を補い、かつ独立した表現形態という流れ。今一つは、絵が重要な役割を担い、絵が物語を引っぱる、いわゆる絵本としての独自の表現形式の流れである。いずれにしても、ダイジェスト化によってアンデルセン童話を多様な視覚表現の世界にひろげたことは間違いない。
複数の場面設定は、描く対象や表現方法を微妙に変化させていった。それまでの独立した絵画的表現から、画面のつながりや一冊全体の構成を意識した表現が見られるようになる。
物語は、どのようなものにしろ時間の流れを伴った通時態である。ある場面を抜き出して絵にすることは、時間の流れを止めたところで描かなければならない。挿絵がそのような共時態の表現だとすれば、絵本は、通時態と共時態を統合していく表現の形態である。しかし、絵物語の成立というのは、時間の流れを絵によってことばと置き換えるということではない。ことばと絵、両方で物語、時間の流れをつくり出す手法と考えるべきだろう。ことばと絵、どちらが主ということではなく、相互に関係しあう表現形態、それが絵本である。
その点から見れば、童話の挿絵と、絵本として描かれたイラストレーションは区別されるべきものである。小説が映画化されるとき、いったん脚本に置き換えられ映像化されるが、童話が絵本化される場合も、脚本こそないがことばとイメージが新たに解釈されて表現されたものである。絵本は、新しい解釈に基づく別のメディアと考えるべきだろう。
日本でのアンデルセン
明治20年代に入ると、主として少年、少女雑誌を中心にアンデルセン童話は次々に紹介された。1891年(明治24)に発行された『二人椋助』は、尾崎紅葉訳で武内桂舟の挿絵が入っているが、多色木版刷りの口絵と本文中には墨版の木版挿絵が挿入されている。文字と絵が融合する構成、和綴じの本ということもあって、江戸以来の絵草紙の形態をそのまま残している。
明治期のアンデルセン童話の受容の仕方がおもしろいのは、主として雑誌では、ほとんどが日本の文化や風俗に合わせて翻案されたことだろう。「二人椋助」は、「大クラウス小クラウス」を日本に設定を置き換えたものであるし、「おやゆびひめ」が「新竹取物語(一名指子姫)」や「花子姫」に変わる。当然、挿絵も着物を着たおやゆびひめになる。翻案されたこれらの物語は、アンデルセン童話がもとになっているにもかかわらず、アンデルセンの名前が記されているものはほとんどない。明治期、アンデルセン童話は、積極的に紹介されているが、アンデルセン童話として翻訳されたものよりも、日本向きに翻案されたものが圧倒的に多いのは、西洋文化の受容の形としても興味深い。
ちなみに翻訳や翻案されたタイトルは、『皇帝の新しい着物』、『マッチ売りの少女』、『絵のない絵本』が群をぬいて多い。それぞれ、「領主の新衣」「裸の王様」、「小サキ引火奴売の童女」「まっち娘」、「王宮」「月物語」などのタイトルで紹介された。挿絵は、小林清親、橋口五葉ら当時名だたる画家たちが担当しているが、和と洋が折衷しつつも造形的には、日本画や木版刷りの伝統を受け継いだものが多い。
明治も40年代になると、西洋の文化が徐々に浸透し、タイトルは「安得仙家庭物語」、「アンデルゼン物語」とはっきりうたわれ、挿絵も原作にそって描いたものが増えていった。それでも、子どものための本の様相が一気に変わるのは大正時代に入ってからである。
近代化の進んだ大都市は、生活や文化の面で新しい姿を見せはじめ、雑誌『白樺』をはじめさまざまな雑誌によって、ヨーロッパの芸術の動向が伝えられた。アールヌーボーなど世紀末芸術から前衛的な1920年代の新しい芸術運動まで、同時に流入してきたのである。若い世代は、新しい表現や思想に敏感に反応し、視覚表現の新しい方法論を造形の面からも、思想的な面からも貪欲に摂取しようとした。
1914年(大正3)、羽仁もと子によって創刊された絵雑誌『子供の友』や1922年(大正11)に創刊された『コドモノクニ』は、竹久夢二、岡本帰一、川上四郎、清水良雄、武井武男、初山滋、村山知義ら新しいタイプの画家たちの活躍の舞台となった。
童画の名称は1924年に開催した「武井武雄童画展」で武井がはじめて使用したものだが、絵雑誌の登場とともに、挿絵や絵本を描く担い手の中心は日本画家の余技から童画家に移っていった。他の絵雑誌と比べて少し大判の『コドモノクニ』は、都市生活と未来に向けた子どもたちの姿が生き生きと描かれている。武井の絵からは、カンディンスキーやパウル・クレーと共通するものを感じるが、西欧の新しい表現様式を日本的な形と色のなかに独自に消化し、イラストレーションに日本的モダニズムを表そうとした。
初山滋がアンデルセン童話のために最初にイラストレーションを描いたのは1925年の『おやゆびひめ』であるが、初山は、ここで徹底的に解釈すること、抽象化することに徹している。当時の挿絵としては極めて斬新なもので、西欧の影響を受けつつも、柔らかな曲線、平面的な構成、モンタージュの試みなど随所に実験的な試みが見られ、その表現性は初山独自のものとなっている。
1920年代は、日本における子どもの本の黄金期といわれるが、それは若い作家が最も高揚し、表現性はもちろん、思想的にも西欧の新しい息吹を同時代的体験として求め、一つの運動体としてあったことも大きい。日本に近代的な絵本が確立していった背景には、旧来の挿絵画家に替わって、新しい思想を持った童画家の台頭と活躍があったことを忘れてはならない。
初山のイラストレーションは、大胆な構成から子ども向きではないと否定的な見方をされたこともある。最初の『おやゆびひめを』見ると、確かに子どもだけを意識して描いたとはあまり思えない。
あらためて「子どものため」について考えるとき、現代の童話や絵本は、「子ども」ということばの呪縛に必要以上に囚われすぎているのではないかと思うことがある。もちろん、「子どものため」に必要な領域の重要性を否定するつもりはないが、童話や絵本は、子どものためのものであると同時に、独自の表現領域であり、大人の心にも響いてこそ、優れた作品といえるのではないか。
例えば、絵本になったアンデルセン童話を見てみると、絵物語として新しいメディアに置き換わっていく一方で、「子どもの本」という枠組みの中に閉じこめられ、アンデルセンが描いた心の機微や世界観がいとも簡単に消されてしまっているものも少なくない。「子ども」を対象にするというだけで、単純で分かりやすいだけの絵物語になってしまうのなら、もはやアンデルセンの絵本と呼べないのではないか。
絵本作家には、アンデルセンがことばで表現したものをイラストレーションで十分表現できる力量が問われる。初山のイラストレーションには、アンデルセンの世界を深く読み込む意識と、独自に解釈し視覚的に具体化しようとした強い情熱が感じられる。アンデルセン童話が200年に渡って読みつがれてきたこと、大人の側からの解釈、大人の読み方も常に話題になってきたことも、決して偶然のことではない。アンデルセン自身、児童文学にこだわらず大人の心にも響くことを意識していたように、アンデルセン童話は、世代を超えて楽しめる環境がもっとあっていいように思う。
「アンデルセン童話とイラストレーション」『アンデルセン生誕200年展』展覧会図録 凸版印刷博物館 2006年2月